映画感想 [2001-2100]
 偉すぎるオッサンたちの死屍累累もリス・エヴァンスの哀しきクローネンバーグ節も、すべては、一夜の事件に長い歳月を錯視させてしまう失恋した夜の体感の肥やしにしてしまう安定のマーク・ウェブ節。
偉すぎるオッサンたちの死屍累累もリス・エヴァンスの哀しきクローネンバーグ節も、すべては、一夜の事件に長い歳月を錯視させてしまう失恋した夜の体感の肥やしにしてしまう安定のマーク・ウェブ節。
 運に寵愛される不安じみたフワフワはビルケナウのゆるふわな対比法で懲罰的に模倣された。しかしその自己顕示的迫力は叙情というよりも叙事を全うできなかったという根性論に人を傾斜させる。
運に寵愛される不安じみたフワフワはビルケナウのゆるふわな対比法で懲罰的に模倣された。しかしその自己顕示的迫力は叙情というよりも叙事を全うできなかったという根性論に人を傾斜させる。
 アンジーの皮を被ったオッサンが外世界へ出奔する脱皮を臨床的に敢行したとき、個人的な体験が歴史感覚に組み込まれ、悲劇を観察した余韻をもたらす。
アンジーの皮を被ったオッサンが外世界へ出奔する脱皮を臨床的に敢行したとき、個人的な体験が歴史感覚に組み込まれ、悲劇を観察した余韻をもたらす。
 ドンソクがキム・ムヨルと取引する必要があるのだろうか。本来ならボーイズ・ラヴを高揚させるはずのその不自然がドンソクのヒロイズムにただ乗りするあまり、童貞やくざ映画という虚無に誤接続する踏み足。
ドンソクがキム・ムヨルと取引する必要があるのだろうか。本来ならボーイズ・ラヴを高揚させるはずのその不自然がドンソクのヒロイズムにただ乗りするあまり、童貞やくざ映画という虚無に誤接続する踏み足。
 コテコテのVシネにナオミ・ワッツの筋が絡むカテゴリーエラーの喜劇は、ヴィゴ・モーテンセンの怖気の振るうナルシシズムに帰着する。文体の模索はとうぜん試みられ、ナルシシズムはポルノの物的な迫力へと発展的に誤用される。しかし落ち着いたところで我に返るのである。すべてがナオミの尻の包摂される真の通俗に至ったのではないかと。
コテコテのVシネにナオミ・ワッツの筋が絡むカテゴリーエラーの喜劇は、ヴィゴ・モーテンセンの怖気の振るうナルシシズムに帰着する。文体の模索はとうぜん試みられ、ナルシシズムはポルノの物的な迫力へと発展的に誤用される。しかし落ち着いたところで我に返るのである。すべてがナオミの尻の包摂される真の通俗に至ったのではないかと。
 あらゆるカテゴリーを包括してきたニューシネマがSFという際物を持て余してしまう。志に撮影の質感が追い付かない安さは、70年代という文明の根源的な安さを検出せざるを得なくなる。だがその安さは帰属先を喪失した感動的な安さなのだ。
あらゆるカテゴリーを包括してきたニューシネマがSFという際物を持て余してしまう。志に撮影の質感が追い付かない安さは、70年代という文明の根源的な安さを検出せざるを得なくなる。だがその安さは帰属先を喪失した感動的な安さなのだ。
 粘りのない老人演出の明るい諦念は人体をカジュアルに破壊する喜劇に想到し、スタローンの安い声音が状況を超越していく。男は無力に頌揚を覚えたのである。
粘りのない老人演出の明るい諦念は人体をカジュアルに破壊する喜劇に想到し、スタローンの安い声音が状況を超越していく。男は無力に頌揚を覚えたのである。
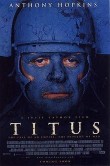 ネタ映画である。旧劇の大仰な芝居から微細な心象がこぼれる隔靴掻痒も、レ〇ターをそんなに挑発していいのかという嬉しいドキドキも、すべて、こんなオファーされて当人怒ってないかというメタな不安にたどり着く。だから問題の場面では想像以上にノリノリで安心してしまった。
ネタ映画である。旧劇の大仰な芝居から微細な心象がこぼれる隔靴掻痒も、レ〇ターをそんなに挑発していいのかという嬉しいドキドキも、すべて、こんなオファーされて当人怒ってないかというメタな不安にたどり着く。だから問題の場面では想像以上にノリノリで安心してしまった。
 能力の定義をめぐる話で、人間の淘汰に関心があるのだから、無能を無能と見せないさじ加減がサスペンス感をもたらし、それはナタリーの焦らしテクとして開花する。断頭音の躊躇のなさにはナタリーがまた酷い目に遭ったというカテゴリー定着の、蒙昧を払いのけるような心地よさすらある。
能力の定義をめぐる話で、人間の淘汰に関心があるのだから、無能を無能と見せないさじ加減がサスペンス感をもたらし、それはナタリーの焦らしテクとして開花する。断頭音の躊躇のなさにはナタリーがまた酷い目に遭ったというカテゴリー定着の、蒙昧を払いのけるような心地よさすらある。
 ヒロインの齧歯目の容貌。息子の巨貌。ベビーコールの憎らしい卵型の膨らみ。この映画の物証性は事件を技術論に押しとどめる。臨床の対象に過ぎなくなった女は恋愛に際しては地雷喚起にしかならず、シャイニングのシェリー・デュヴァルのように顔芸の方が怖い。他方で技術論は女を戦闘力のキレの内に覚醒させ、この難渋から芸術的感興を引き出してもくれる。結末は中身に反して意外と軽やかである。
ヒロインの齧歯目の容貌。息子の巨貌。ベビーコールの憎らしい卵型の膨らみ。この映画の物証性は事件を技術論に押しとどめる。臨床の対象に過ぎなくなった女は恋愛に際しては地雷喚起にしかならず、シャイニングのシェリー・デュヴァルのように顔芸の方が怖い。他方で技術論は女を戦闘力のキレの内に覚醒させ、この難渋から芸術的感興を引き出してもくれる。結末は中身に反して意外と軽やかである。
 女児が性愛という自然に乗っ取られることも、カウンセラーの誘導尋問が無能の迫力を以て事態を膨張させるのも、何かに身を委ねることへの愛癖だ。男の根性論がその隷従のヒロイズムを克服するも、根性は同時に女難という結論にも近接して冒頭の全裸オッサンらの戯れに回帰する。
女児が性愛という自然に乗っ取られることも、カウンセラーの誘導尋問が無能の迫力を以て事態を膨張させるのも、何かに身を委ねることへの愛癖だ。男の根性論がその隷従のヒロイズムを克服するも、根性は同時に女難という結論にも近接して冒頭の全裸オッサンらの戯れに回帰する。
 無為徒食者の停滞が年齢不詳という形で時を止める。何もかもを景物で埋めたがるこの業界の美的感覚は時を空間で代行する営みである。しかし滞留という詩趣は人々のIQを容赦なく可視化していく。
無為徒食者の停滞が年齢不詳という形で時を止める。何もかもを景物で埋めたがるこの業界の美的感覚は時を空間で代行する営みである。しかし滞留という詩趣は人々のIQを容赦なく可視化していく。
 ローラ・ダーンの内村光良顔がホワイトトラッシュの質感にふれたとき、北米がロシアンパブに覆われていく。その偶発的な軟地盤は構造物を彷徨ううれしさをともないつつ、納品は終わったのに疲弊で不機嫌しか残らない負の達成感に物質的土台を獲得する。
ローラ・ダーンの内村光良顔がホワイトトラッシュの質感にふれたとき、北米がロシアンパブに覆われていく。その偶発的な軟地盤は構造物を彷徨ううれしさをともないつつ、納品は終わったのに疲弊で不機嫌しか残らない負の達成感に物質的土台を獲得する。
 細部に悲酸が宿るほど経済問題のない介護物の浮遊感は否めなくなるが、そのフワフワを逆手にとって、トランティニャンは気品を隠せない自身の西村晃声に導かれ運命の虐待から卓越していく。その際、イザベル・ユペールのテンパりが対比として効いてくる。
細部に悲酸が宿るほど経済問題のない介護物の浮遊感は否めなくなるが、そのフワフワを逆手にとって、トランティニャンは気品を隠せない自身の西村晃声に導かれ運命の虐待から卓越していく。その際、イザベル・ユペールのテンパりが対比として効いてくる。
 いい大人が眉間に皴を寄せてエントロピーだのプルトニウムだのと言葉を交わす罰ゲームのような安さ。セイリングでキレのない体を持て余すエリザベス・デビッキのタヌキ顔が全てをヒモのDV劇へ矮小化する。ラストバトルとカットバックする夫婦漫才が深夜ドンキの駐車場という情念で以て安さを小説化するのだ。
いい大人が眉間に皴を寄せてエントロピーだのプルトニウムだのと言葉を交わす罰ゲームのような安さ。セイリングでキレのない体を持て余すエリザベス・デビッキのタヌキ顔が全てをヒモのDV劇へ矮小化する。ラストバトルとカットバックする夫婦漫才が深夜ドンキの駐車場という情念で以て安さを小説化するのだ。
 磯野家をミサイルが直撃するのはこの手のジャンルとしては常套としても、順序がおかしいから本当にいきなり直撃してしまう。直撃後の漂流の尺が長い。それがおかしいのである。暴力の強度で謂えば、漂流の場面は磯野家とミサイルの中間であり磯野家とミサイルの緩衝となったはずだ。これが順序を間違えているから理知的な先生が発狂するのも無理はない。Uボートのような結末に至っては疫病神が災厄を招き寄せたような事件の社会化の迫力さえある。
磯野家をミサイルが直撃するのはこの手のジャンルとしては常套としても、順序がおかしいから本当にいきなり直撃してしまう。直撃後の漂流の尺が長い。それがおかしいのである。暴力の強度で謂えば、漂流の場面は磯野家とミサイルの中間であり磯野家とミサイルの緩衝となったはずだ。これが順序を間違えているから理知的な先生が発狂するのも無理はない。Uボートのような結末に至っては疫病神が災厄を招き寄せたような事件の社会化の迫力さえある。
 元々奇人のジム・キャリーである。マスクを被る意味はないのだが、筋をコメディの文法に依存しないことで、話は安心できる正調のクライムムービーとなっている。美人の心理にアプローチすることでキャメロンの好意は正当化され、ブンヤのエイミー・ヤスベックの不自然な好意もやはり合理化される。
元々奇人のジム・キャリーである。マスクを被る意味はないのだが、筋をコメディの文法に依存しないことで、話は安心できる正調のクライムムービーとなっている。美人の心理にアプローチすることでキャメロンの好意は正当化され、ブンヤのエイミー・ヤスベックの不自然な好意もやはり合理化される。
 キャストの骨相がここまで多様なのは珍しく、しかもそれは演出の不在ではない。椎名桔平の行き場のないナルシシズムが美女に転生するオッサンたちという邪念によって換喩されるアクロバットなのである。真っ先に殺されそうな杉本哲太がわけのわからないまま誰よりも真相に近づくのも深い。
キャストの骨相がここまで多様なのは珍しく、しかもそれは演出の不在ではない。椎名桔平の行き場のないナルシシズムが美女に転生するオッサンたちという邪念によって換喩されるアクロバットなのである。真っ先に殺されそうな杉本哲太がわけのわからないまま誰よりも真相に近づくのも深い。
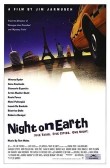 人の発見に長けたこの密室劇は、ベニーニのサイコ性をも的確に抽出せざるを得ない。前半の人情噺はこれでぶち壊しになるも、諦観に安住する趣味の悪いヘルシンキの結末にサイコの物的な迫力が何かしらの感慨をもたらしていると思う。
人の発見に長けたこの密室劇は、ベニーニのサイコ性をも的確に抽出せざるを得ない。前半の人情噺はこれでぶち壊しになるも、諦観に安住する趣味の悪いヘルシンキの結末にサイコの物的な迫力が何かしらの感慨をもたらしていると思う。
 長期的な利益を鑑みても答えは明らかでありパチーノが師父をやる余地はなく、自殺幇助を強制する迷惑な話にとどまっている。パチーノの哀れに注力しても中盤のタンゴがピークアウトになる。文芸的に苦しむのは校長のジェームズ・レブホーンとシーモアの方であって、殊に終盤はシーモアの演技がパチーノを喰ってしまっている。
長期的な利益を鑑みても答えは明らかでありパチーノが師父をやる余地はなく、自殺幇助を強制する迷惑な話にとどまっている。パチーノの哀れに注力しても中盤のタンゴがピークアウトになる。文芸的に苦しむのは校長のジェームズ・レブホーンとシーモアの方であって、殊に終盤はシーモアの演技がパチーノを喰ってしまっている。
 エド・スクラインの顔面映画である。エメリッヒ作品の湿ったセクシャリティを濃縮したようなあの顔が、極彩色の海原上をスペルマの飛沫の如く飛び交う曳光弾をかいくぐり、トヨエツ&浅野の二大ネオモンゴロイド顔と交錯。國村隼を大いに困惑させる淫猥さである。
エド・スクラインの顔面映画である。エメリッヒ作品の湿ったセクシャリティを濃縮したようなあの顔が、極彩色の海原上をスペルマの飛沫の如く飛び交う曳光弾をかいくぐり、トヨエツ&浅野の二大ネオモンゴロイド顔と交錯。國村隼を大いに困惑させる淫猥さである。
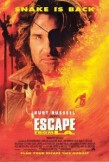 役者根性を試しにかかるこのコスチューム劇はラッセルをナルシシズムに憩わせない。劇中で幾度も自己言及される彼の体のバランスの悪さは、ルームランナー、グライダー、津波を通じて罰ゲームのように絶えず実体化される。この間の悪さにブシェーミのサヴァイヴ劇ががぶり寄る恵み深いカーペンター節。
役者根性を試しにかかるこのコスチューム劇はラッセルをナルシシズムに憩わせない。劇中で幾度も自己言及される彼の体のバランスの悪さは、ルームランナー、グライダー、津波を通じて罰ゲームのように絶えず実体化される。この間の悪さにブシェーミのサヴァイヴ劇ががぶり寄る恵み深いカーペンター節。
 チョン・ジヒョンの薄幸力がベルリンを神田川三畳一間の情調へ落とし込む。もともとベルリンで事をやる意味がない以上、窮乏が神田川三畳下宿へ空間を改編して舞台の必然性を調達する。その編成の媒質としての、リュ・スンボムの西村ひろゆき顔の明るき寄る辺なさ。
チョン・ジヒョンの薄幸力がベルリンを神田川三畳一間の情調へ落とし込む。もともとベルリンで事をやる意味がない以上、窮乏が神田川三畳下宿へ空間を改編して舞台の必然性を調達する。その編成の媒質としての、リュ・スンボムの西村ひろゆき顔の明るき寄る辺なさ。
 悲劇を喜劇の間合いで同定するスノビズムを牧師クラウスナーのヒール化が克服する。なぜ悲劇が楽しいのか。物語は懲悪という娯楽の実践へ送り返されたのである。
悲劇を喜劇の間合いで同定するスノビズムを牧師クラウスナーのヒール化が克服する。なぜ悲劇が楽しいのか。物語は懲悪という娯楽の実践へ送り返されたのである。
 鶴田浩二のスケベが筋に組み込まれるように、出来事を構造に織り込む力は彼を津川雅彦の物語の傍観者にしておかない。軟体のように伸びる鶴田の鼻の下は、丹波哲郎の棒読みに繰り込まれるまま、任侠映画という構造そのものに達する。それは津川の勇気を培養する羊膜なのだ。
鶴田浩二のスケベが筋に組み込まれるように、出来事を構造に織り込む力は彼を津川雅彦の物語の傍観者にしておかない。軟体のように伸びる鶴田の鼻の下は、丹波哲郎の棒読みに繰り込まれるまま、任侠映画という構造そのものに達する。それは津川の勇気を培養する羊膜なのだ。
 ナルシシズムを散らすための客観視のツールとして喜劇を用いるならばオッサンの邪念はむしろ加速するはずだ。そうではなく、伊丹十三の怪演を分水嶺にして、むしろこのハーレムが喜劇の必然性の根拠となる。
ナルシシズムを散らすための客観視のツールとして喜劇を用いるならばオッサンの邪念はむしろ加速するはずだ。そうではなく、伊丹十三の怪演を分水嶺にして、むしろこのハーレムが喜劇の必然性の根拠となる。
 器質性に基づく苦悶を精神論でアプローチしようとするパターナリズムはどうなのか。小泉今日子の、顔貌とアニメ声のミスマッチが究極的には女難として徴表されることで作者の自意識が明らかになるが、事件に応じて浅野忠信の人柄が一定しなくなるのも事実で、この人たちは何を悩んでいたのか戸惑いが残る。
器質性に基づく苦悶を精神論でアプローチしようとするパターナリズムはどうなのか。小泉今日子の、顔貌とアニメ声のミスマッチが究極的には女難として徴表されることで作者の自意識が明らかになるが、事件に応じて浅野忠信の人柄が一定しなくなるのも事実で、この人たちは何を悩んでいたのか戸惑いが残る。
 フレームに寄られるたびに長澤まさみの姉御顔が春秋戦国を足立区へ変貌させる。コスチュームプレイに羞恥を覚えるどころか、むしろ水を得たように大沢たかおはナルシシズムの光耀に満たされる。髙嶋政宏を笑い走らせない恐るべき統制力と技術力が話を吉沢亮のナンパテク観察記に終わらせない。
フレームに寄られるたびに長澤まさみの姉御顔が春秋戦国を足立区へ変貌させる。コスチュームプレイに羞恥を覚えるどころか、むしろ水を得たように大沢たかおはナルシシズムの光耀に満たされる。髙嶋政宏を笑い走らせない恐るべき統制力と技術力が話を吉沢亮のナンパテク観察記に終わらせない。
 絵沢萠子との絡みでは、現金仕送りの件がそうであるように、善と生活力の優れた例化が観測できる。他人の悲劇に基づく喚情には節度があって、それが内藤陳の好ましい機能的色彩と呼応する。ルビー・モレノとの顛末を見れば、岸谷五朗の不自然なガタイが社会時評の躁宴を制した感がある。
絵沢萠子との絡みでは、現金仕送りの件がそうであるように、善と生活力の優れた例化が観測できる。他人の悲劇に基づく喚情には節度があって、それが内藤陳の好ましい機能的色彩と呼応する。ルビー・モレノとの顛末を見れば、岸谷五朗の不自然なガタイが社会時評の躁宴を制した感がある。
 発情持続症というべき無感動への憎悪が軽演劇を連ねるうちに笑いという無感動を偶に掘り当ててしまう。これはまぐれではなくて稽古量が即興という印象を与えないのである。
発情持続症というべき無感動への憎悪が軽演劇を連ねるうちに笑いという無感動を偶に掘り当ててしまう。これはまぐれではなくて稽古量が即興という印象を与えないのである。
 人権侵害を捌口にして、渡瀬恒彦にアドレナリンは、抑えるために誇張する老け演技の矛盾へと解き放たれる。平幹二朗の会社の応接間で前衛的な夕日に映えるその死神の相貌は、志村けん声の調べを宰領しつつ、誰も幸せにならなかったというセンチメンタリズムの揺曳に慰藉を見出す悦ばしき趣味の悪さに達する。
人権侵害を捌口にして、渡瀬恒彦にアドレナリンは、抑えるために誇張する老け演技の矛盾へと解き放たれる。平幹二朗の会社の応接間で前衛的な夕日に映えるその死神の相貌は、志村けん声の調べを宰領しつつ、誰も幸せにならなかったというセンチメンタリズムの揺曳に慰藉を見出す悦ばしき趣味の悪さに達する。
 メタボ特有の陽気な感じが事を悲劇にするはずがなく、喜劇に向かおうにも、恐怖を特定しその尺度を担うはずの霊能者が錯乱しているから、悲劇か喜劇かの舵取りに能わない。結果、中盤以降、アンサンブル・キャストが互いに進行を打ち消し合う停滞に見舞われ、話がでかくなる様がカジュアルに死体の山を築き上げる力技に依存してしまっている。
メタボ特有の陽気な感じが事を悲劇にするはずがなく、喜劇に向かおうにも、恐怖を特定しその尺度を担うはずの霊能者が錯乱しているから、悲劇か喜劇かの舵取りに能わない。結果、中盤以降、アンサンブル・キャストが互いに進行を打ち消し合う停滞に見舞われ、話がでかくなる様がカジュアルに死体の山を築き上げる力技に依存してしまっている。
 寝袋や焚火といったガジェットから野宿者の徳を構成するミニマリズムが、回顧的に見れば80年代半ばという定義しにくい時代を無時間へと転用して、ノスタルジーを凌駕している。
寝袋や焚火といったガジェットから野宿者の徳を構成するミニマリズムが、回顧的に見れば80年代半ばという定義しにくい時代を無時間へと転用して、ノスタルジーを凌駕している。
 このキャスティングの違和感は、中尾彬の顔面が最後はモンタージュ写真へと解体されて事が瓦解することで報われている。千葉真一の便利さも筋のスポイルではなく下士官の忠誠として読み解かれる。話自体は序盤のスティングでピークアウトするも、夏木や中尾の顔圧に丸め込まれた感じは決して不快ではない。
このキャスティングの違和感は、中尾彬の顔面が最後はモンタージュ写真へと解体されて事が瓦解することで報われている。千葉真一の便利さも筋のスポイルではなく下士官の忠誠として読み解かれる。話自体は序盤のスティングでピークアウトするも、夏木や中尾の顔圧に丸め込まれた感じは決して不快ではない。
 余貴美子と井川遥が鶴瓶を追い詰める男性嫌悪が、最後の鶴瓶を死神のように解釈させる誤配に至っている。この話の技術志向が、劇中で自己言及されるように、事を自己決定権の問題ではなく医療過誤に見せてしまうからだ。語り口はあくまで美談扱いだから混乱甚だしい。
余貴美子と井川遥が鶴瓶を追い詰める男性嫌悪が、最後の鶴瓶を死神のように解釈させる誤配に至っている。この話の技術志向が、劇中で自己言及されるように、事を自己決定権の問題ではなく医療過誤に見せてしまうからだ。語り口はあくまで美談扱いだから混乱甚だしい。
 全貌の露見に至って判然となるのは、隠蔽された筋というよりはむしろ、おかしなことをおかしく表現してきた舞台調のオーヴァーアクトによって仕込まれていた誠意の圧である。一連の事件を多部未華子に繋げてしまうのは流石にどうかと思われるが、誠意に流されるという背徳に跳躍を賭けるのである。
全貌の露見に至って判然となるのは、隠蔽された筋というよりはむしろ、おかしなことをおかしく表現してきた舞台調のオーヴァーアクトによって仕込まれていた誠意の圧である。一連の事件を多部未華子に繋げてしまうのは流石にどうかと思われるが、誠意に流されるという背徳に跳躍を賭けるのである。
 昼間からラーメンと焼酎を喰らっても悲酸を呈しない円楽のキレ具合。顔貌と釣り合わない夏目雅子の昭和な形姿。マグロの、如何にもマグロな覇気のない殺戮。場末を模倣しようとしたアイドル映画の文体的内破である。
昼間からラーメンと焼酎を喰らっても悲酸を呈しない円楽のキレ具合。顔貌と釣り合わない夏目雅子の昭和な形姿。マグロの、如何にもマグロな覇気のない殺戮。場末を模倣しようとしたアイドル映画の文体的内破である。
 江戸東京博物館の常設展示的バロックというべき意匠の欠如。それをまとめ得る田中邦衛の悲劇が、勝新の諦観をミスリードする遠心力に巻き込まれる。劇の構造はぼやけ続け、死に花を咲かせと自己顕示欲が互いを包含する。
江戸東京博物館の常設展示的バロックというべき意匠の欠如。それをまとめ得る田中邦衛の悲劇が、勝新の諦観をミスリードする遠心力に巻き込まれる。劇の構造はぼやけ続け、死に花を咲かせと自己顕示欲が互いを包含する。
 岩下志麻(40)をセーラー服で飾る超時間感覚が虚偽記憶の寓意となる。無駄に悶絶する杉浦直樹から名古屋章に至る、80年代の絢爛なオッサンコレクションに際し、増村保造の叙法は頑としてノスタルジーを拒絶するのだ。
岩下志麻(40)をセーラー服で飾る超時間感覚が虚偽記憶の寓意となる。無駄に悶絶する杉浦直樹から名古屋章に至る、80年代の絢爛なオッサンコレクションに際し、増村保造の叙法は頑としてノスタルジーを拒絶するのだ。
 田植え、介護等々、永島敏行が徳の実践を重ねる程に、かえってアタラクシアの危うさが喚起される。モンテーニュによれば、もっとも美しい生活とは奇蹟も異常もない生活であるそうだが、石田えりとのミュージカルでその徳操が至るのは、幸福、あるいは希少性自体が含有する哀切である。
田植え、介護等々、永島敏行が徳の実践を重ねる程に、かえってアタラクシアの危うさが喚起される。モンテーニュによれば、もっとも美しい生活とは奇蹟も異常もない生活であるそうだが、石田えりとのミュージカルでその徳操が至るのは、幸福、あるいは希少性自体が含有する哀切である。
 作者の相対主義によるかく乱に抗するのは、ケイン号のメカメカしさと共鳴するボガートの器質的リアリズムである。パラノイアを享楽する役者根性がいじめを介護問題のつらさへと組み替る。不幸の遍し流布が達せられ、受け手は公平を期したい緊張から解放される。
作者の相対主義によるかく乱に抗するのは、ケイン号のメカメカしさと共鳴するボガートの器質的リアリズムである。パラノイアを享楽する役者根性がいじめを介護問題のつらさへと組み替る。不幸の遍し流布が達せられ、受け手は公平を期したい緊張から解放される。
 挿話が使い捨てにされない。本筋が人の性格を説明するイベントも兼ねる。ミッキーのダンディズムがナルシシズムに墜ちないのも筋の経済性の賜物だろう。が、この蓋然性の牢獄は勝新がどんどん掘り当てていく善人たちを曼荼羅のような統一体へはめ込んでしまう。互いに固着するところに善は生じるが、その非弾力性で収拾がつかないのである。
挿話が使い捨てにされない。本筋が人の性格を説明するイベントも兼ねる。ミッキーのダンディズムがナルシシズムに墜ちないのも筋の経済性の賜物だろう。が、この蓋然性の牢獄は勝新がどんどん掘り当てていく善人たちを曼荼羅のような統一体へはめ込んでしまう。互いに固着するところに善は生じるが、その非弾力性で収拾がつかないのである。
 80年代の豊饒が場末感を許さないから、叙法はスコセッシ&レオ的なドラッグムービーに似てくる。それは好ましい皮相であって、悲惨を餌食としはしない高潔が、矢吹二朗という俳優の実存論になっている。
80年代の豊饒が場末感を許さないから、叙法はスコセッシ&レオ的なドラッグムービーに似てくる。それは好ましい皮相であって、悲惨を餌食としはしない高潔が、矢吹二朗という俳優の実存論になっている。
 永作博美に月並みな挫折をもたらす人間の上げ下げの螺旋運動が、キャラに対する公平性を維持したまま懲悪的没落のスペクタクルを達成する。その緊張の圧縮の譜調が啓蒙する、蒼井優スケコマシへの神々しい道程。
永作博美に月並みな挫折をもたらす人間の上げ下げの螺旋運動が、キャラに対する公平性を維持したまま懲悪的没落のスペクタクルを達成する。その緊張の圧縮の譜調が啓蒙する、蒼井優スケコマシへの神々しい道程。
 筋はつながらない。技術力がカットはつなげてしまう。阪妻の不可解な情熱は技術の例化なのだが、偶然以外に阪妻と交信する術のない水戸光子は宗教的情熱という放心に至り、頻度ないし霊感に交信を賭ける。終局で阪妻は妻の放心に呼応する。彼は煙に巻かれて実体を失う。
筋はつながらない。技術力がカットはつなげてしまう。阪妻の不可解な情熱は技術の例化なのだが、偶然以外に阪妻と交信する術のない水戸光子は宗教的情熱という放心に至り、頻度ないし霊感に交信を賭ける。終局で阪妻は妻の放心に呼応する。彼は煙に巻かれて実体を失う。
 希少なれば使い込みたくなる聖人の駆動力が落伍者の成瀬正孝の人生と絡むどころか打ちのめしにかかるから、渡瀬恒彦から希少性を奪わずにはいられなくなる。人間の自律が主題に容嫁する自我の緊張が、徹夜明けのようなフワフワとしたつらみとして鬱積する。
希少なれば使い込みたくなる聖人の駆動力が落伍者の成瀬正孝の人生と絡むどころか打ちのめしにかかるから、渡瀬恒彦から希少性を奪わずにはいられなくなる。人間の自律が主題に容嫁する自我の緊張が、徹夜明けのようなフワフワとしたつらみとして鬱積する。
 常に観測に晒される岸部一徳こそ、岩松了ら狂人たちの楽しい旅路を客体化している。ランダムに顔を出すパレードのような恣意的誠意に回転木馬搭乗者の羞恥感が発見され、綺麗事が花やしきへと包摂される。
常に観測に晒される岸部一徳こそ、岩松了ら狂人たちの楽しい旅路を客体化している。ランダムに顔を出すパレードのような恣意的誠意に回転木馬搭乗者の羞恥感が発見され、綺麗事が花やしきへと包摂される。
 死んだり蘇ったり、実に忙しい。雌が強すぎる気まずい三角関係は特異な死生観の結果なのか。生物の必然性から逸脱した事態に際して、感情を文芸的に拗らせようもなく困惑するジョン・ボイエガ。対してアダム・ドライバーの馬面が為す術もなく伸びやかになる特殊顔相学の夕べ。
死んだり蘇ったり、実に忙しい。雌が強すぎる気まずい三角関係は特異な死生観の結果なのか。生物の必然性から逸脱した事態に際して、感情を文芸的に拗らせようもなく困惑するジョン・ボイエガ。対してアダム・ドライバーの馬面が為す術もなく伸びやかになる特殊顔相学の夕べ。
 パンパンに膨れ上がった小池朝雄の頬が圧となって、ナルシシズムに酩酊する藤純子の鼻筋を事件に組み込んでいく。論理の運びに身を任せ、いつしかアラカンの頑張に「親分! 親分!」と盛り上がってしまう嬉し恥ずかし。
パンパンに膨れ上がった小池朝雄の頬が圧となって、ナルシシズムに酩酊する藤純子の鼻筋を事件に組み込んでいく。論理の運びに身を任せ、いつしかアラカンの頑張に「親分! 親分!」と盛り上がってしまう嬉し恥ずかし。
 斉藤由貴を頂点とする恐るべき群集自己愛劇。ただ一人自己愛を抑圧する松岡茉優の眼力は、腸からの失気を恐れるかのように不自然だ。遠雷とは自己愛の腹鳴。心傷への酔い痴れには漏れ出る気体の芳しさがある。
斉藤由貴を頂点とする恐るべき群集自己愛劇。ただ一人自己愛を抑圧する松岡茉優の眼力は、腸からの失気を恐れるかのように不自然だ。遠雷とは自己愛の腹鳴。心傷への酔い痴れには漏れ出る気体の芳しさがある。
 90年代の根津甚八は甚八であることがさぞかし気持ちよかったであろう。甚八も夏川結衣も互いに自分のことしか考えない。甚八はおのれの性欲に敗北したのではなく、性欲は夜霧のように輪郭を曖昧にして拡散した。スケベとナルシシズムの共和国で不幸の物量が効力を失う。重喜劇の読後感だ。
90年代の根津甚八は甚八であることがさぞかし気持ちよかったであろう。甚八も夏川結衣も互いに自分のことしか考えない。甚八はおのれの性欲に敗北したのではなく、性欲は夜霧のように輪郭を曖昧にして拡散した。スケベとナルシシズムの共和国で不幸の物量が効力を失う。重喜劇の読後感だ。
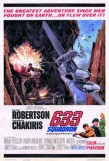 実機とセットの機内を繋ぐのは俳優の顔芸。ヨットから家族へと話題を繋げ、人へ共感を向かわせるのは論理である。ハリー・アンドリュースの顎が青空に映える。待ち人の苦しさでその顎はどこまでも伸び渡り、やがて全てを包摂しねじ伏せたのだ。
実機とセットの機内を繋ぐのは俳優の顔芸。ヨットから家族へと話題を繋げ、人へ共感を向かわせるのは論理である。ハリー・アンドリュースの顎が青空に映える。待ち人の苦しさでその顎はどこまでも伸び渡り、やがて全てを包摂しねじ伏せたのだ。
 類型を同定する力は自分を知りたい願望であり、その副作用たる脊髄反射の集積としての生体の機械観(ピアノで発情!)。その実体化としての悪趣味寸前の美術の集積度。作者の好きなものしかそこには映らない。自分の中に没落していくその無窮動の威力。
類型を同定する力は自分を知りたい願望であり、その副作用たる脊髄反射の集積としての生体の機械観(ピアノで発情!)。その実体化としての悪趣味寸前の美術の集積度。作者の好きなものしかそこには映らない。自分の中に没落していくその無窮動の威力。
 試合運びを作者の価値観に隷属させる没精神の営みで冷笑を克服するジレンマ。作為の強烈さは筋を訓致できても実体は騙せない。没精神的な追憶は、後日談での三人の正気を疑う衣装として外化する。
試合運びを作者の価値観に隷属させる没精神の営みで冷笑を克服するジレンマ。作為の強烈さは筋を訓致できても実体は騙せない。没精神的な追憶は、後日談での三人の正気を疑う衣装として外化する。
 不幸は拡散することで人を繋ぐ。拡散には空間が必要だ。空間を描画するのは、おしめ探索による遠近法である。理詰めの筋はドミノ倒しのように軽く忙しく疑似家族を流転させる。引きとどめるのは加藤嘉の類型の重さである。
不幸は拡散することで人を繋ぐ。拡散には空間が必要だ。空間を描画するのは、おしめ探索による遠近法である。理詰めの筋はドミノ倒しのように軽く忙しく疑似家族を流転させる。引きとどめるのは加藤嘉の類型の重さである。
 疑似方言が劇を様式優先にするのだが、外観は博多で中身がシリアという曲芸がこれと合わない。事件と心理劇が交差せずに並走し、大道芸が話を進ませない。かろうじて磁場となるのは学園物という叙法。
疑似方言が劇を様式優先にするのだが、外観は博多で中身がシリアという曲芸がこれと合わない。事件と心理劇が交差せずに並走し、大道芸が話を進ませない。かろうじて磁場となるのは学園物という叙法。
 表現を顔貌に頼れないなら行動の人になる他ない。多動の人々が一定の空間に追い込まれ、机を組み合わせる落ちゲーに勤しみ、感情の物体化を試みる。現実化さるべき彼岸は土曜半ドンのノスタルジーという台風明けの霊界だ。
表現を顔貌に頼れないなら行動の人になる他ない。多動の人々が一定の空間に追い込まれ、机を組み合わせる落ちゲーに勤しみ、感情の物体化を試みる。現実化さるべき彼岸は土曜半ドンのノスタルジーという台風明けの霊界だ。
 声だけ聴いてれば原田芳雄パロで済ませられる。ガタイが異なるから、原田を肉体の内に同定できない腹話術のような実存の不安が生じる。それはトランスジェンダーのような中性的な口振りであったり、重心の高さも手伝って、歩くだけで曲芸になってしまう体のブレであったり。総じていえば、安定感抜群の内田朝雄の頭頂を支点にしたヤジロベエである。
声だけ聴いてれば原田芳雄パロで済ませられる。ガタイが異なるから、原田を肉体の内に同定できない腹話術のような実存の不安が生じる。それはトランスジェンダーのような中性的な口振りであったり、重心の高さも手伝って、歩くだけで曲芸になってしまう体のブレであったり。総じていえば、安定感抜群の内田朝雄の頭頂を支点にしたヤジロベエである。
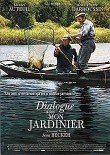 スタローン(ダニエル・オートゥイユ)が画家? このミスキャストは実は正しい。重病人をルーヴルで連れまわす肉体派の奇行が、生体としてのジャン=ピエール・ダルッサンにわれわれをコミットさせる。スタローンの暗喩する肉体がものをいうのだ。
スタローン(ダニエル・オートゥイユ)が画家? このミスキャストは実は正しい。重病人をルーヴルで連れまわす肉体派の奇行が、生体としてのジャン=ピエール・ダルッサンにわれわれをコミットさせる。スタローンの暗喩する肉体がものをいうのだ。
 障害者の性の問題をこの時代の倫理コードが主題化できる訳がない。不安な感じだけが何事かに帰着するのである。IQが高いという叙事の好ましさが悪事という叙情を圧殺。伏線の回収が気持ちよすぎて、回収される内容が問われなくなるのだ。
障害者の性の問題をこの時代の倫理コードが主題化できる訳がない。不安な感じだけが何事かに帰着するのである。IQが高いという叙事の好ましさが悪事という叙情を圧殺。伏線の回収が気持ちよすぎて、回収される内容が問われなくなるのだ。
 美術にせよ蟹江敬三にせよ、作り込みが場末を侘び寂びのスノビズムに解消してしまう。発声ができてない本間優二の天然がこれを救うかというと、頭から声が出てる感じが、やはり人を理屈に走らせてしまう。助平だけが、最後にヒラヒラする沖山秀子だけが、地上を救うのである。
美術にせよ蟹江敬三にせよ、作り込みが場末を侘び寂びのスノビズムに解消してしまう。発声ができてない本間優二の天然がこれを救うかというと、頭から声が出てる感じが、やはり人を理屈に走らせてしまう。助平だけが、最後にヒラヒラする沖山秀子だけが、地上を救うのである。
 宍戸錠、そのアンパンマンのような頬が小林千登勢に惹かれ膨張する。膨張の極限には自壊がある。おのれの頬と向き合った彼は独り埋立地に赴く。頬の膨らみを遮るものはもはやない。が、次の瞬間、それは穿孔に嵌る。その快。
宍戸錠、そのアンパンマンのような頬が小林千登勢に惹かれ膨張する。膨張の極限には自壊がある。おのれの頬と向き合った彼は独り埋立地に赴く。頬の膨らみを遮るものはもはやない。が、次の瞬間、それは穿孔に嵌る。その快。
 オカルトへの憎しみと女性嫌悪が互換してしまった。感情をあくまで顔容に委託する演出が終局的にこれらを揚棄して失恋を可能にするメカニズムは、やはり塚本・諸星らしく、どこまでも物象の誇張である。
オカルトへの憎しみと女性嫌悪が互換してしまった。感情をあくまで顔容に委託する演出が終局的にこれらを揚棄して失恋を可能にするメカニズムは、やはり塚本・諸星らしく、どこまでも物象の誇張である。
 表現主義が通俗の筋に落ち込むのを嫌う一方、筋の幾何学性への好みは否定しようがなく、表現主義に適う形で筋の痕跡を把捉しようとする。あの喫茶店で、厭々に店番を営むうちに、体は経営センスを隠せなくなってしまう。
表現主義が通俗の筋に落ち込むのを嫌う一方、筋の幾何学性への好みは否定しようがなく、表現主義に適う形で筋の痕跡を把捉しようとする。あの喫茶店で、厭々に店番を営むうちに、体は経営センスを隠せなくなってしまう。
 モブが事態を傍観している。感情はすべて講述される。これは演出の不在である。前半と後半の筋が関連を持たない。これは脚本の不在である。台詞の間が小津映画のような几帳面さで12コマずつ区切られている。これは編集の不在である。この体系のなさは、体系がない苦しみにヒロイズムを見ずにはいられない。しかしそれは夢を見る。体系なき分業が有機体に至る夢を。
モブが事態を傍観している。感情はすべて講述される。これは演出の不在である。前半と後半の筋が関連を持たない。これは脚本の不在である。台詞の間が小津映画のような几帳面さで12コマずつ区切られている。これは編集の不在である。この体系のなさは、体系がない苦しみにヒロイズムを見ずにはいられない。しかしそれは夢を見る。体系なき分業が有機体に至る夢を。
 観光とナンパから始まって挙句にKKKから宗教右派へ。御曹司集団劇という特殊形態の中にやがて何とも抗しがたいベンアフ文芸の秘密が花開く。ダイコンという恒常性の船に乗って、波乱にとんだ世界の荒波を彼は乗り切ったのである。
観光とナンパから始まって挙句にKKKから宗教右派へ。御曹司集団劇という特殊形態の中にやがて何とも抗しがたいベンアフ文芸の秘密が花開く。ダイコンという恒常性の船に乗って、波乱にとんだ世界の荒波を彼は乗り切ったのである。
 内面のわからない人であるから、この男をどう扱ったのかという、たとえば六平直政のように周縁の人物を聖化する方向へ自ずと進み、その究極として樋口可南子の聖母化であるが、そこで気づくのである。アキレスとは男の内面であり、樋口の聖性を経由してようやくそこに到達したと。
内面のわからない人であるから、この男をどう扱ったのかという、たとえば六平直政のように周縁の人物を聖化する方向へ自ずと進み、その究極として樋口可南子の聖母化であるが、そこで気づくのである。アキレスとは男の内面であり、樋口の聖性を経由してようやくそこに到達したと。
 コーカソイドへのコンプレックスと裏返しとしてのモンゴロイド憎悪。これらのゼノフォビアの間で地元武士団への感情が行き場を失う。日本語話者の受け手としては機械的に好意は覚えるのだけども彼らの動機には惹かれるものがない。このモヤモヤはアステアのような重力のないアクションとして時に外化するようにも思う。
コーカソイドへのコンプレックスと裏返しとしてのモンゴロイド憎悪。これらのゼノフォビアの間で地元武士団への感情が行き場を失う。日本語話者の受け手としては機械的に好意は覚えるのだけども彼らの動機には惹かれるものがない。このモヤモヤはアステアのような重力のないアクションとして時に外化するようにも思う。
 懲悪物に全振りはしない。山田孝之の悪がある域を超えると、綾野剛から突っ込みが入る。ストレスがなくてよい。終盤の堺 vs 山田はワンカットのむつかさしさで、憎悪というより配慮の作劇に見えてしまう。殊に堺についていえば、キレのよい動きをいかに押しとどめるか苦慮する自閉した戦いに終始している。それは、慈悲心で燃え上がるという矛盾の顛末である。
懲悪物に全振りはしない。山田孝之の悪がある域を超えると、綾野剛から突っ込みが入る。ストレスがなくてよい。終盤の堺 vs 山田はワンカットのむつかさしさで、憎悪というより配慮の作劇に見えてしまう。殊に堺についていえば、キレのよい動きをいかに押しとどめるか苦慮する自閉した戦いに終始している。それは、慈悲心で燃え上がるという矛盾の顛末である。
 不可能がない状況依存的文学が教養小説として急激に構造化する。完成した人間しか出てこない任侠物の様式に70年代らしい立体感が与えられる。
不可能がない状況依存的文学が教養小説として急激に構造化する。完成した人間しか出てこない任侠物の様式に70年代らしい立体感が与えられる。
 油断すると綾瀬はるかが大沢たかおへモーフィングしてしまう。オダギリ・染谷・松重がタイプキャストの重みと笑いで威しつけていた像を結べないその奇禍は、岸壁を走る綾瀬の意外な身体能力なる、いかにも映画的な事態で破綻を来す。陰伏的に内包された佐藤健のヒモ生活の不安が?き出しとなるのだ。
油断すると綾瀬はるかが大沢たかおへモーフィングしてしまう。オダギリ・染谷・松重がタイプキャストの重みと笑いで威しつけていた像を結べないその奇禍は、岸壁を走る綾瀬の意外な身体能力なる、いかにも映画的な事態で破綻を来す。陰伏的に内包された佐藤健のヒモ生活の不安が?き出しとなるのだ。
 堺雅人に話にしかならない自覚が手術ネタを空転させた結果、堺が真中瞳の自愛のオカズにしかなっていないような迫力へと転倒が起こる。あのほくろが本体であるような怯えとともに、野趣の晴れやかさが広がる。救いの手が勝手にやってくるハーレム映画がほくろの吸引力を実証し、身体機構を一個の徳にするのである。
堺雅人に話にしかならない自覚が手術ネタを空転させた結果、堺が真中瞳の自愛のオカズにしかなっていないような迫力へと転倒が起こる。あのほくろが本体であるような怯えとともに、野趣の晴れやかさが広がる。救いの手が勝手にやってくるハーレム映画がほくろの吸引力を実証し、身体機構を一個の徳にするのである。
 森谷司郎の初々しい演出に円谷の操演が追い付けず、佐藤充を多動させて本編はストレスを訴えるも、谷幹一との漫才が佐藤を御し得て唯物的な円谷特撮を克服する。堕ちる加山の機影が詩的比喩で以て本編と特撮を終局的に揚棄したのだ。
森谷司郎の初々しい演出に円谷の操演が追い付けず、佐藤充を多動させて本編はストレスを訴えるも、谷幹一との漫才が佐藤を御し得て唯物的な円谷特撮を克服する。堕ちる加山の機影が詩的比喩で以て本編と特撮を終局的に揚棄したのだ。
 場末が場末になりきれない極彩色の地獄が歪ませる空間感覚。緊張の幕間に火遊びをして釣りをやるオフビートで歪む時間感覚。時空からの疎外された人間の荒廃した境遇を作者は観察するだけだが、詠嘆が叙景で代替されるに及んで視点だけは50年代時空を回収する。
場末が場末になりきれない極彩色の地獄が歪ませる空間感覚。緊張の幕間に火遊びをして釣りをやるオフビートで歪む時間感覚。時空からの疎外された人間の荒廃した境遇を作者は観察するだけだが、詠嘆が叙景で代替されるに及んで視点だけは50年代時空を回収する。
 『男たちの大和』がプライベート・ライアンならば、こちらはポセイドン・アドベンチャーの趣で、個々人の生存の可否に受け手の興趣を賦活させる手管に優れる。財津&中井親子の長生きネタなどは、論理志向が過ぎてブラックヒューモアに近い。
『男たちの大和』がプライベート・ライアンならば、こちらはポセイドン・アドベンチャーの趣で、個々人の生存の可否に受け手の興趣を賦活させる手管に優れる。財津&中井親子の長生きネタなどは、論理志向が過ぎてブラックヒューモアに近い。
配役はもはやむちゃくちゃである。鉄面皮の佐藤慶すらストレスを被る戦況で、何気に生存してマイペースをかます丹波。ここに鶴田浩二を参戦させるカオスはどうかと思えば、決戦前夜の見回りで筋に恐怖の生々しさを帰責する。最後は谷村新司と中野昭慶爆発で漲る喪失感。80年代邦画の幕開けに相応しい代物だ。
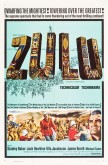 火工品の響きを吸収するように、肉に着弾する鉄片だけは音もなくめり込み、人体から生理的琴線を奪う。何度も壊れては蘇り、戦場をいつまでも構造化できない陣地。所縁なき戦場で最後に寄る辺となったのはリージョナリズムの精神性。
火工品の響きを吸収するように、肉に着弾する鉄片だけは音もなくめり込み、人体から生理的琴線を奪う。何度も壊れては蘇り、戦場をいつまでも構造化できない陣地。所縁なき戦場で最後に寄る辺となったのはリージョナリズムの精神性。
 藤岡弘が顔圧が新時代川北特撮を加速させれば、負けじと対峙する丹波&平田昭彦の旧人類組。横暴なる顔圧の狭間で平準化した、陸攻搭乗員たちの顔貌は諦念の微笑へと加工され、主題へ最も接近する。
藤岡弘が顔圧が新時代川北特撮を加速させれば、負けじと対峙する丹波&平田昭彦の旧人類組。横暴なる顔圧の狭間で平準化した、陸攻搭乗員たちの顔貌は諦念の微笑へと加工され、主題へ最も接近する。
 景物映画に相応しく老人は一個の静物に還ろうとしている。時を知らぬ物はその同時性をランダムな記憶へと翻訳する。が、主客をぼかす客体化の衝動は技術的要件の支配でもある。もっとやりようがあったのでは。そう思わせてしまう。
景物映画に相応しく老人は一個の静物に還ろうとしている。時を知らぬ物はその同時性をランダムな記憶へと翻訳する。が、主客をぼかす客体化の衝動は技術的要件の支配でもある。もっとやりようがあったのでは。そう思わせてしまう。
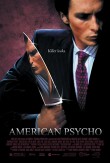 80年代に見えるか? 見えるはずがない。にもかかわらず、クロエ・セヴィニーの巨大な肩パットを目撃すると無性に泣けてくる。郷愁の催涙感を人間への憐憫にすり替えるのである。クロエの善良さは、クリスチャン・ベールの人の好さを活かすが、これではアメリカン・サイコでも何でもない。マンハッタンは西新宿と化し80年代が捕捉される。審美と倫理が互換した瞬間に立ち会ったわけである。
80年代に見えるか? 見えるはずがない。にもかかわらず、クロエ・セヴィニーの巨大な肩パットを目撃すると無性に泣けてくる。郷愁の催涙感を人間への憐憫にすり替えるのである。クロエの善良さは、クリスチャン・ベールの人の好さを活かすが、これではアメリカン・サイコでも何でもない。マンハッタンは西新宿と化し80年代が捕捉される。審美と倫理が互換した瞬間に立ち会ったわけである。
 トラブルに惹かれる男と旅グルメ。バラエティショーの番組フォーマットを援用しながらも、60年代ディープサウス紀行の社会時評はトラブルとグルメを離断せずにはいられない。文脈から浮き上がる健啖家の食欲は能天気という得難い徳を謳う。
トラブルに惹かれる男と旅グルメ。バラエティショーの番組フォーマットを援用しながらも、60年代ディープサウス紀行の社会時評はトラブルとグルメを離断せずにはいられない。文脈から浮き上がる健啖家の食欲は能天気という得難い徳を謳う。
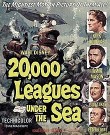 触手に見舞われてもカーク・ダグラスの逃亡癖が危機を中和する(なぜ艦を救う必要が?)。ひげ面まみれの叙景にかろうじて迂遠な一体感をもたらすのは、動く非日常ピーター・ローレの困惑顔。精神安定を希求するかのように、そのイガグリがやたらと撫でられるのである。
触手に見舞われてもカーク・ダグラスの逃亡癖が危機を中和する(なぜ艦を救う必要が?)。ひげ面まみれの叙景にかろうじて迂遠な一体感をもたらすのは、動く非日常ピーター・ローレの困惑顔。精神安定を希求するかのように、そのイガグリがやたらと撫でられるのである。
 地上人の啓蒙はそのまま肯ずるには気持ちがよすぎる。肉体派の楽園がそこに掣肘を加えバランスはとれたように見える。が、ラブコメの冴えわたる手腕が肉体派を無邪気なロマネスクに隷属させ、すべては文系男の極彩色の邪念に飲み込まれるうれしいオチであった。
地上人の啓蒙はそのまま肯ずるには気持ちがよすぎる。肉体派の楽園がそこに掣肘を加えバランスはとれたように見える。が、ラブコメの冴えわたる手腕が肉体派を無邪気なロマネスクに隷属させ、すべては文系男の極彩色の邪念に飲み込まれるうれしいオチであった。
 予感される教訓は、女にとってみれば、バンドマンに引っかかってはならぬ。男に喚起されるのは、ミシェル・ウィリアムズという類型配役。文系を幾人も殺害してきたそのタヌキ顔。教化は現前したといえなくもないが、男は何となく破局するのであり社会的文脈とはつながらない。他方、かかる模糊模糊しさは踊り歌うタヌキ顔のお宝度に転義され、謎の説得力を恵与する。
予感される教訓は、女にとってみれば、バンドマンに引っかかってはならぬ。男に喚起されるのは、ミシェル・ウィリアムズという類型配役。文系を幾人も殺害してきたそのタヌキ顔。教化は現前したといえなくもないが、男は何となく破局するのであり社会的文脈とはつながらない。他方、かかる模糊模糊しさは踊り歌うタヌキ顔のお宝度に転義され、謎の説得力を恵与する。
 状況だけに好意の物証を追及する情熱は、背徳のスリラーを景物映画で展開する越境を志向する。関係の逆転に伴って、背徳感は性欲一般に備わる喜劇性に代わり、結末の傷心に緩和すると思う。自分が本妻であるという生物的確信は痛憤の情を遠ざけ、むしろ遠距離恋愛のような甘い語脈に通ずる。
状況だけに好意の物証を追及する情熱は、背徳のスリラーを景物映画で展開する越境を志向する。関係の逆転に伴って、背徳感は性欲一般に備わる喜劇性に代わり、結末の傷心に緩和すると思う。自分が本妻であるという生物的確信は痛憤の情を遠ざけ、むしろ遠距離恋愛のような甘い語脈に通ずる。
 フィクションの侵食先は現実にとどまらない。その侵食力が編集者の躯幹と交織すると、土着メディアが異文明を併呑する量感に圧される。劇中劇の劇伴に本編のそれが被るような現実腐蝕の力は欧米人に土下座をも強いる迫力で希望の押し売りを超えていく。
フィクションの侵食先は現実にとどまらない。その侵食力が編集者の躯幹と交織すると、土着メディアが異文明を併呑する量感に圧される。劇中劇の劇伴に本編のそれが被るような現実腐蝕の力は欧米人に土下座をも強いる迫力で希望の押し売りを超えていく。
 テイラー・シェリダンの男たちは性欲に負けない。むしろ性欲を恃みとする。そのままではキャバクラ説教の背徳になりかねないジェレミーの眉間の皴が社会化すれば、啓蒙思想家が頭で考えたような正義の有り様となり、視象に帰着するとワイオミングの冬空に映える死化粧の白塗りと交歓し、相応の詩的密度を達成する。
テイラー・シェリダンの男たちは性欲に負けない。むしろ性欲を恃みとする。そのままではキャバクラ説教の背徳になりかねないジェレミーの眉間の皴が社会化すれば、啓蒙思想家が頭で考えたような正義の有り様となり、視象に帰着するとワイオミングの冬空に映える死化粧の白塗りと交歓し、相応の詩的密度を達成する。
 マザコンの愛妻家は性欲の未分化と思うのだが、性欲よりも分化の方に重点はあるようで、事態を動かす母と息子の共犯関係に沿って怨念が分化して精緻化される。ダメ母を暗黒面に落とす勧善懲悪の含みは、203高地のようなストレスとの対峙劇に代わる。闇落ちした男は肉体に怨恨の物証を求め、その狂奔する肉化が涙と笑いを訴える。
マザコンの愛妻家は性欲の未分化と思うのだが、性欲よりも分化の方に重点はあるようで、事態を動かす母と息子の共犯関係に沿って怨念が分化して精緻化される。ダメ母を暗黒面に落とす勧善懲悪の含みは、203高地のようなストレスとの対峙劇に代わる。闇落ちした男は肉体に怨恨の物証を求め、その狂奔する肉化が涙と笑いを訴える。
 少年を見た大人たちの反応は自分の善性がかき立てられる機会を得たよろこびを湛えている。徳のかかる反匿名性は少年に受恵者のプレッシャーをもたらし、その顔に異化を絶やさない。かつ、善の衝動は流れるように円滑な懲悪をも成功させている。
少年を見た大人たちの反応は自分の善性がかき立てられる機会を得たよろこびを湛えている。徳のかかる反匿名性は少年に受恵者のプレッシャーをもたらし、その顔に異化を絶やさない。かつ、善の衝動は流れるように円滑な懲悪をも成功させている。
 GUIがなぜラスターでなくベクトルで描画されるのか。そして、オヤジさんに凌駕される警察はどれだけ無能なのか。いずれも合理化はされるのである。が、無能に無能を重ねる形で無能が合理化されるために、フラクタルの再帰に飲み込まれるような不快になってしまう。どこまで拡大できるベクトルデータが
意味を持ってしまう。
GUIがなぜラスターでなくベクトルで描画されるのか。そして、オヤジさんに凌駕される警察はどれだけ無能なのか。いずれも合理化はされるのである。が、無能に無能を重ねる形で無能が合理化されるために、フラクタルの再帰に飲み込まれるような不快になってしまう。どこまで拡大できるベクトルデータが
意味を持ってしまう。
 人間よりもAIの動機がはるかに強い。彼らは生死を脅かされている。事件の端緒は恋を覚えたAIに発している。AIを現実の踏み台にしたのは誤りだろう。作者がAIの恋に気をやった痕跡はあるが、解法が見つからなかったのか、その顛末は投げ出しに近い。踏み台に過ぎないため、フリー・シティでもフリー・ライフでもAIの挙動に差が見えてこない。
人間よりもAIの動機がはるかに強い。彼らは生死を脅かされている。事件の端緒は恋を覚えたAIに発している。AIを現実の踏み台にしたのは誤りだろう。作者がAIの恋に気をやった痕跡はあるが、解法が見つからなかったのか、その顛末は投げ出しに近い。踏み台に過ぎないため、フリー・シティでもフリー・ライフでもAIの挙動に差が見えてこない。
 途中で物語の進行が友人ポール・ウォルター・ハウザーに依存してしまい、薄弱なるものへの憎悪とそれが退治される懲悪の心地よさが、格差や文化資本の問題を無効にする。ハウザー退治の後は消化試合となり、後日談では悪友から解放された安堵が広がる始末である。
途中で物語の進行が友人ポール・ウォルター・ハウザーに依存してしまい、薄弱なるものへの憎悪とそれが退治される懲悪の心地よさが、格差や文化資本の問題を無効にする。ハウザー退治の後は消化試合となり、後日談では悪友から解放された安堵が広がる始末である。
 当時も今も様子が変わらない意味で寺は時を知らない。バブルの風俗が寺の時のなさの前提となるが、時がないから本木雅弘が最初から完成されている。むしろ関係は逆流して、無時間性がバブルと今と媒介しそれをノスタルジーに翻案し始める。西新宿、柄本明オフィスの催涙的なユートピア便り。対して、寺の無時間を担保するのが竹中直人の美声と下士官的挙措のリズムである。
当時も今も様子が変わらない意味で寺は時を知らない。バブルの風俗が寺の時のなさの前提となるが、時がないから本木雅弘が最初から完成されている。むしろ関係は逆流して、無時間性がバブルと今と媒介しそれをノスタルジーに翻案し始める。西新宿、柄本明オフィスの催涙的なユートピア便り。対して、寺の無時間を担保するのが竹中直人の美声と下士官的挙措のリズムである。
 いつものことながら、イ・ビョンホンの、つまり北のエージェントの動機が強すぎてハ・ジョンウの本編が延々とコメディリリーフになるアジア的映画風景が展開する。ビョンホンに対抗できるようなジョンウの悲劇はいかにして可能か。コメディリリーフは逆用されダメ男という生物的関心へ向かう。ところが第三者にはポカンとするような強烈な社会時評が生物的関心の遠心力となってしまう。この綱引きがそもそも筋をコメディリリーフにするのだが、遠心力が空間に現象すると火山灰の廃野という不実定の眺めとなる。
いつものことながら、イ・ビョンホンの、つまり北のエージェントの動機が強すぎてハ・ジョンウの本編が延々とコメディリリーフになるアジア的映画風景が展開する。ビョンホンに対抗できるようなジョンウの悲劇はいかにして可能か。コメディリリーフは逆用されダメ男という生物的関心へ向かう。ところが第三者にはポカンとするような強烈な社会時評が生物的関心の遠心力となってしまう。この綱引きがそもそも筋をコメディリリーフにするのだが、遠心力が空間に現象すると火山灰の廃野という不実定の眺めとなる。
 ケイシー・アフレックの髭面が被り物をしている。これは評価が難しい。髭面はシーツ幽霊の可愛さを損なうのか。中身が髭面だからこそ切なくなるのか。ベートーベンの講話を何分も聞かされる。何が悲しくてハゲを延々と見せられるのか。しかしその硬質な頭皮が次第にケイシーの髭面を鎮静する。幽霊譚がウロボロスになるのはアイデアだが、これは全うできない。受け手を手紙で散々引っ張った上であのオチでは作法に反するといわれても仕方がない。
ケイシー・アフレックの髭面が被り物をしている。これは評価が難しい。髭面はシーツ幽霊の可愛さを損なうのか。中身が髭面だからこそ切なくなるのか。ベートーベンの講話を何分も聞かされる。何が悲しくてハゲを延々と見せられるのか。しかしその硬質な頭皮が次第にケイシーの髭面を鎮静する。幽霊譚がウロボロスになるのはアイデアだが、これは全うできない。受け手を手紙で散々引っ張った上であのオチでは作法に反するといわれても仕方がない。
 グロリアをアンジーのアイドル映画にしては疑似母性どころではない。性欲を不幸の顕示癖として叙述するシェリダン節が今回は分裂している。アンジーは惜しげもなく不幸を衒うがカワイイから許したい。語り手の性欲は少年に仮託されたといえなくもない。これが山火事に塗れるとジャンルが不明瞭になり、フワフワしてくる。その帰結としての露天風呂である。
グロリアをアンジーのアイドル映画にしては疑似母性どころではない。性欲を不幸の顕示癖として叙述するシェリダン節が今回は分裂している。アンジーは惜しげもなく不幸を衒うがカワイイから許したい。語り手の性欲は少年に仮託されたといえなくもない。これが山火事に塗れるとジャンルが不明瞭になり、フワフワしてくる。その帰結としての露天風呂である。
 そもそも完成されている少年少女なので成長譚としては弱く、むしろ少年少女地獄変であり、折角築かれたオッサンらの屍の山が無駄に見えてしまう。オッサン側についていえば、今回はブローリンに筋の重心あり、お守り役のデル・トロは傍流で、これも成長譚を弱める原因となる。最後の恐怖の生徒指導室のように今回のデル・トロはネタ要員である。オッサンを立てたいのか、オッサンを踏み台にして成長譚をやりたいのか、語り手がブレるのである。
そもそも完成されている少年少女なので成長譚としては弱く、むしろ少年少女地獄変であり、折角築かれたオッサンらの屍の山が無駄に見えてしまう。オッサン側についていえば、今回はブローリンに筋の重心あり、お守り役のデル・トロは傍流で、これも成長譚を弱める原因となる。最後の恐怖の生徒指導室のように今回のデル・トロはネタ要員である。オッサンを立てたいのか、オッサンを踏み台にして成長譚をやりたいのか、語り手がブレるのである。
 男の内面が受け手には見えてなかったと判明する類の話であり、見えないものを見えてるつもりにさせる、つまり無意識に形式を与える作業は筋の運びを類比的にせずにはいられない。そのトラウマがなつかしのポップカルチャとして転義するのは芸である。内面の仮象に形を与えるライリー・キーオの文系殺しのかわゆさもきわめて映画的な事態だろう。
男の内面が受け手には見えてなかったと判明する類の話であり、見えないものを見えてるつもりにさせる、つまり無意識に形式を与える作業は筋の運びを類比的にせずにはいられない。そのトラウマがなつかしのポップカルチャとして転義するのは芸である。内面の仮象に形を与えるライリー・キーオの文系殺しのかわゆさもきわめて映画的な事態だろう。
 これでは格差の批評が成り立たないではないか。太い実家のクラスメートと対置しても、学力が高すぎるために、秀才組にも先天的要因の介在が見えてしまい、メリトクラシーを貫徹できなくなる。学力が換金できる作中の事態が、不正がなくとも中長期的にはあの学力は換金可能と予想させるために、貧困脱出から切実さは消え不正への情熱が徒労に見えてくる。
これでは格差の批評が成り立たないではないか。太い実家のクラスメートと対置しても、学力が高すぎるために、秀才組にも先天的要因の介在が見えてしまい、メリトクラシーを貫徹できなくなる。学力が換金できる作中の事態が、不正がなくとも中長期的にはあの学力は換金可能と予想させるために、貧困脱出から切実さは消え不正への情熱が徒労に見えてくる。
 この密室スリラーは基本的に八百長であり悲劇は偶然に依存している。そして偶発はスリラーになりえない。作者は現場レベルの正義の担保に興味があり、市警と州警察と州兵のパワーバランスのなかで各々がキャラ立ちを果たし、加害者のストレスに話は傾斜していく。受け手には感情をぶつける的に欠けがちで、終盤の法廷劇も均整なき筋をさらに取り留めなくしている。
この密室スリラーは基本的に八百長であり悲劇は偶然に依存している。そして偶発はスリラーになりえない。作者は現場レベルの正義の担保に興味があり、市警と州警察と州兵のパワーバランスのなかで各々がキャラ立ちを果たし、加害者のストレスに話は傾斜していく。受け手には感情をぶつける的に欠けがちで、終盤の法廷劇も均整なき筋をさらに取り留めなくしている。